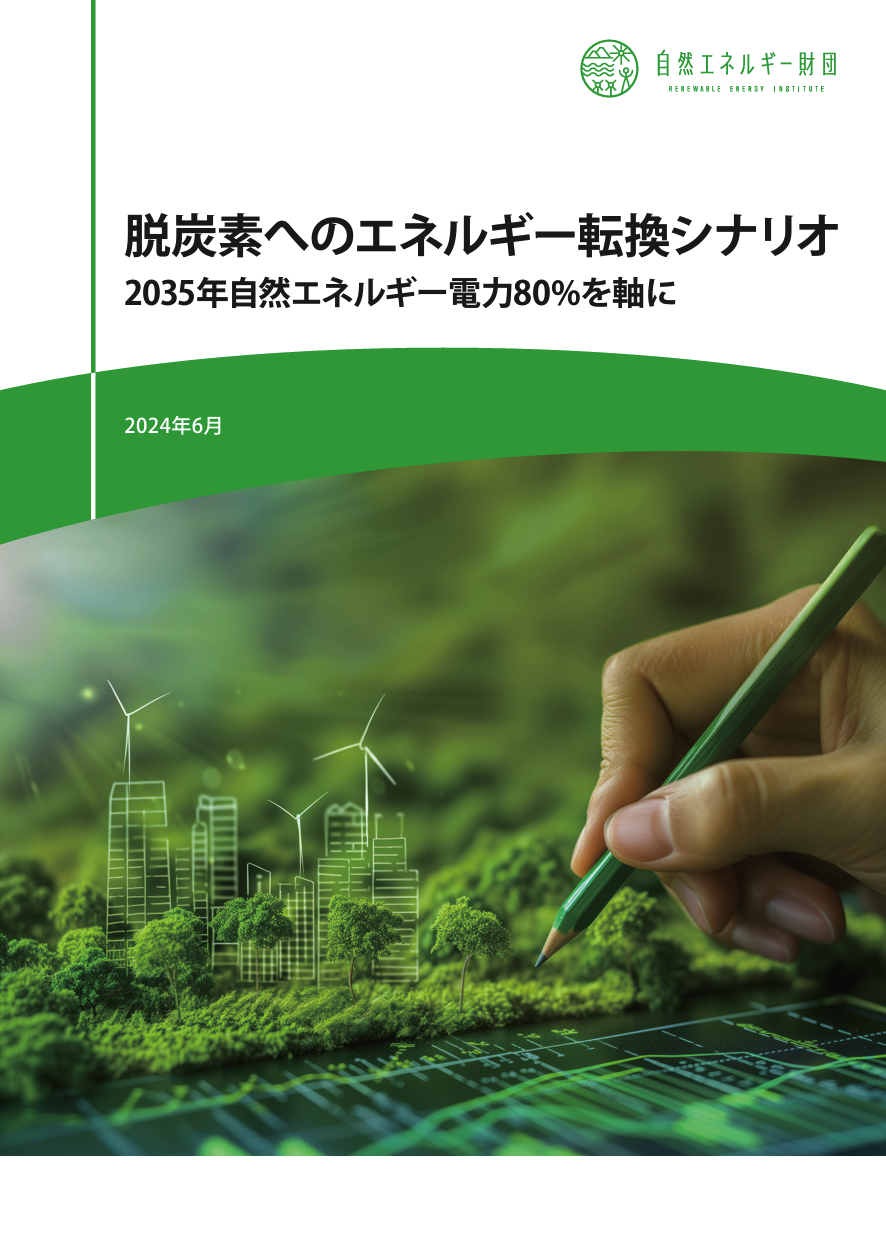インサイト
better business decisions
日本のエネルギーの未来:2035年までに再生可能エネルギー80%を目指す戦略
公益財団法人 自然エネルギー財団は、2035年度までに日本の再生可能エネルギーの割合を80%に引き上げることが可能だという分析を報告しました。この目標を達成するためには、蓄電池の導入拡大や地域電力網の強化が鍵となります。現在の22%から急増させ、同時に石炭火力や原子力の廃止を目指す計画です。さらに、電気料金の上昇や産業活動への影響を最小限に抑えつつ、CO2排出量を大幅に削減することが期待されています。これらのエネルギー転換は、電力消費が安定していることを前提としており、電気料金の大幅な上昇や産業活動への影響なしに実現することが可能で、データセンターや半導体産業の成長にもかかわらず、電力消費は効率化により抑えられると見られています。

報告書概要
再生可能エネルギーの拡大
日本はすでに22%の再生可能エネルギー比率を持っており、2035年までにこれを80%まで引き上げる計画です。特に太陽光発電と風力発電が中心となり、蓄電池の導入と送電網の強化が不可欠です。蓄電池の容量は現在の1.8GWから72GWに拡大される予定で、昼間の余剰太陽光電力を夜間に使用することで、電力供給の安定性が高まります。
蓄電池と水素エネルギー
蓄電池は、昼間に発生する余剰な太陽光発電電力を蓄え、夜間や風が少ない時期に供給する役割を果たします。また、余剰電力を利用して水素を生成することで、自然エネルギーのさらなる活用が可能になります。この水素エネルギーは将来的に、輸送や産業の脱炭素化にも利用されると予想されています。
送電網とインフラの強化
日本国内の電力網の強化が計画されています。特に、北海道から東京を結ぶ広域送電網の強化が必要です。これにより、風力発電が盛んな地域で発生した電力を都市部に効率的に送電でき、国内全体で安定的なエネルギー供給が可能になります。
CO2排出削減と経済影響
報告書では、2035年までに日本のCO2排出量を2019年比で65%削減することを目指しています。この削減は、産業の電化や省エネ技術の導入によって実現されます。これにより、半導体工場やデータセンターの誘致が進み、国内産業の成長が期待されます。
産業と新エネルギーシステムへの影響
産業部門では、鉄鋼業の電炉化が進み、CO2排出削減に大きく貢献します。電炉化された鉄鋼生産は、自然エネルギーを利用しながら生産され、デマンドレスポンスを通じて電力供給の調整にも貢献します。新しい産業、特に半導体工場やデータセンターの誘致が進むことで、国内の電力需要が増加する一方で、電力の効率化も進むとされています。
コストとエネルギー安全保障
自然エネルギーの導入によって、電力コストはウクライナ危機以前の水準に戻ると推計されています。これは、化石燃料依存の低減により、国際市場の価格変動リスクを抑えられるためです。また、日本は自然エネルギーが豊富な国であり、国産エネルギーの利用を進めることでエネルギー安全保障が強化され、エネルギーの安定供給が確保されます。
また、日本政府は来年、新たなエネルギーミックス計画を策定予定であり、エネルギー需要増加に対応するために原子力への依存度が高まる可能性があります。しかし、再生可能エネルギーの導入拡大により、脱炭素化と持続可能なエネルギー供給が同時に推進されることが期待されています。
このエネルギー転換によって、日本は2019年比でCO2排出量を65%削減することができ、国際的な温暖化抑制目標に沿った取り組みが進むでしょう。日本は今後、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立を図りつつ、地域経済の発展やエネルギー価格の抑制にも取り組むことが期待されています。
自然エネルギー財団について:
自然エネルギー財団(Renewable Energy Institute)は、2011年に孫正義氏によって設立された日本のシンクタンクで、再生可能エネルギーの導入拡大と持続可能なエネルギー社会の実現を目指しています。設立の背景には、2011年の東日本大震災と福島第一原発事故があり、エネルギー政策の見直しが求められる中で誕生しました。財団は、政策提言、研究、国際的な協力を通じて、日本と世界のエネルギー転換を推進しています。